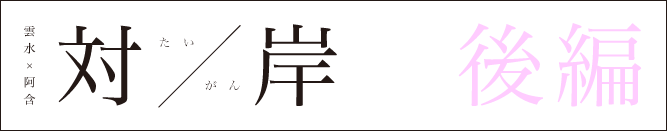花など何処にも見当たらなかった。
見当たらなかったが、俺は促されるままに黙って雑草の上へ腰を下ろした。
すぐに缶ビールを手渡される。缶ビールは意外なほどに冷たかった。
春とはいえ川面を吹き抜けてくる風の冷たさに、シャツ一枚の身は心もとない。
手のなかの缶ビールは強引に他人の手で空けられ、そのまま手首を引かれるとそこには4つの缶が待ち構えていた。
「カンパーイ」
まだ手が、震えていた。
手はフライの皿を引っくり返したときからずっと、震えているように思う。
雲水を突き飛ばした時も、玄関の扉を慎重に閉めた時も。
どうせ風呂へ入るまでの事だと、俺は家へ帰っても家着に着替えることをせず、学生服の上を脱いだだけの格好だった。
そしてその格好のまま、上も羽織らずに家を飛び出した。
四月も後半とはいえ、夜は冷え込む。たった一枚だけのシャツの白さが寒々しい。
家を出てずいぶん歩いたと思うが、神経がくるったように高ぶっていて、今の今まで何も感じなかったのだ。
ひたすらに歩いた。駅へむかうこの川沿いの道を歩くうち、対岸の建物に光が灯っていることに気付いた。
ほかに建物のない川べりにぽつんと建った3階のコンクリートの箱には、うらぶれた個人事務所や、どこかの社長婦人が道楽で始めたような美容がらみの会社や、中高年むけのパソコン教室なんかが出たり入ったり、テナントは常に空きがちだったが、今はまるごと大手学習塾が借りきっている。雲水の通っている学習塾だ。
足を止めて数秒後、足下から俺を呼ぶ声がした。
すぐ下は土手で、その土手の傾斜を滑り降りると川までの数十メートルは原っぱになっている。
陽のあるうちには犬や老人が散歩をしたり、少年サッカーの練習場になったりする。
しかし夜の川原はのっぺりとしていて、全くひとけはない。
街頭の光すらまばらな夜の川原に好んで来る人間はまずいない。
こんな時間に居るのはせいぜい、鬱憤のやり場と、身の置き場のない若者くらいなものだ。
見知った顔が4人、酒盛りをしていた。
皆デニムにナイロンパーカーといった私服姿であった。
地元高校のグレーのジャケットではコンビニで酒を買うことは不可能なのだから当然だろう。
土手を降りてみればなるほど、谷底のようなそこは土手が壁となって、道路むこうの民家からは死角となっている。
花が一本もないことを除けば、未成年の花見にはうってつけの場所であった。
去年の夏に酔っ払ってロケット花火を打ち上げた際には、近所の老人にもの凄い剣幕で怒鳴られたのだが、ただの酒盛りならば何度もここでこうしてやっていると、彼らは得意げだった。
何時であるのかはすでに不明だった。
家を出たのが8時かそこらだったとして、10時か11時か、はたまたとうに日付が変わっているのか。
ただ相当に飲んだ。
缶入りカクテルと銘打ったそれはパッケージこそこぎれいに取り繕っているが、中身は人口甘味料で味付けされた粗悪な工業製品で、アルコール度数の低さとは裏腹に、みるみる神経が痺れていった。
それに気付いたのは、用を足しに立った後だった。
用を足すといっても自分が今尻を落ち着けている草っぱらから少し離れた草っぱらで用を足して、もとの草っぱらへ戻るだけのことだ。
4月も半ばを過ぎ、活気づいてきた草は踏んでも弾力があり、足元はふわふわと安定しなかった。
赤い欄干の橋のたもとにある学習塾の光も傾いで見えた。
まだ電気がついている。
用を足して戻ると場が妙な雰囲気に変わっていることにすぐに気付いた。
人の話はろくに聞かず、自分は愚にもつかないことを大声で話し、大げさに笑い転げ、時に吼え、歌うという落ち着きなく散漫だった彼らの空気が、ひとつに統一されているような緊張感あるものに変わっていた。
先ほどまで熱心にしていた、現国教師の彼氏の有無という下らない討論はどこへやったものか、阿含の一挙手一投足を、盗むように監視するような目つきが4人ともそっくりだった。
一人があごんに座れよ、と言ったなら残りの3人も座をあけたりなどして着席を促す。まるで主役が登場したとばかりの扱いだ。
無意識に手をやったそこに、煙草はなかった。
ポケットに煙草の入ったジャケットは家に置きっぱなしだ。
「煙草か?」
すると鼻先に一本の煙草が突き出された。
不審だったのは、その煙草には火がついていたことだ。
長さはまだ十分に長いが、煙の匂いのするそれが吸いさしであることは明らかだった。
口に銜えずして煙草に火をつけることはできない。
「エンリョすんな」
人差し指と中指に挟んだそれをぐいと突きつけられる。
4人の男の視線が自分に集まっていた。
その、暗闇で息を殺して光るような8つの眼を見、川の風に吹き上げられてジリと短くなる煙草の先を見て、阿含はこれは契約ごとなのだと気付いた。
一学年上の彼らは馬鹿だが、年下の自分に金や物をケチった事だけはなかった。
煙草がなければ箱ごと投げてよこした。
それが、今に限って吸いさしを突きつけてきたのだ。
並んだ男の顔を一人ずつ見る。眼の表面には薄幕のようににはさあどうするよ、とでも言いたげな下卑た哂いが浮かんでいた。
でもそれは装ってるだけだ。「もしダメだったとき」の為のポーズだ。
薄幕のむこうには、この俺に対する欲望だ。
唇を、首筋を、露出している皮膚という皮膚を。胸を、腰を、布を通り抜けて4人の視線が舐め回るのがわかる。
シャツ一枚の肌寒さが、シャツ一枚であるがゆえに火照るような気がした。
薄くひらいた口の向こう、奴らの舌が熱く濡れていることがわかる。
アルコールまじりの息が荒く速いことがわかる。
選択を迫られている。
突きつけられた吸いさしを、俺がどうするのか。
奴等はそれを視ている。
煙草に眼を戻すと視線がいっそうきつく体に絡みついた。
ジリ、焦れるように赤い点が白い線を侵食する。
突き出されたこれを咥えれば。
予感に思わず、喉が鳴った。
ただ一本の八重桜は、盛りの花弁にたっぷりと水分を吸い滴らせ、どこまでも重く、細い枝にぶらさがるようにして為すがまま、ぐったりと雨粒に打たれている。
一重咲きのソメイヨシノはすでに盛りをすぎ、濡れたグラウンドに桜貝を撒いたように散っていた。
枝は既に若い緑を誇っている。
花の季節は終わったのだ。
少なくとも、校庭を縁取るように植えられたソメイヨシノは終わっていた。
借り物のビニール傘にも一枚、花びらが張り付いている。
傘の柄を握る手の甲に、細かな傷がいくつかついている。
紙で切ったような浅く短い直線の赤。
塞がりかけのその傷だけが、阿含に「言い訳」を与えていた。傷同様に小さくつまらない言い訳。
阿含がたっぷりと肺に煙を満たすのを待ってから、それは始まった。
阿含にとって幸いだったのは、彼らが本気で阿含を押さえつけてくれた事だ。表情からは浮かべていた薄笑いを取り払い、必ず成し遂げるという強い欲望を持って阿含を蹂躙しにかかってくれた。
押し倒した一人が阿含の膝を割り、阿含の頭側の一人が両手首を掴みあげた。仰向けにさらけ出された阿含のシャツを一人が剥ぎ取り、一人は自らの衣服を脱ぎにかかった。
相手は年上で体格も上で、4人がかりだ。
それが、彼らが阿含にくれた言い訳だった。
とても抗いきれるものではなかったのだという。
今になれば茶番劇でしかなかったのだが、その時の阿含には十分だった。
彼らは一言もしゃべらず、きゅうきゅうと薄くとがった草の擦れあうせわしない音と、変則的な荒い吐息、川の流れる音だけが阿含の耳に聞こえていた。
まるで肉食獣についばまれる荒野の死体になったようだと、抵抗という抵抗をほとんどしなかった阿含はぼんやりと思った。月も出ていない。
対岸の光も男たちの影になって今はもう見えない。
暴力はなかった。
阿含の体についた傷は、草で切れた手の甲のこまかな傷だけだった。
挿入の瞬間、それはやはり激痛を感じたが、それを暴力と呼ぶには違和感がある。
それはシャワーまで浴びてベッドの上でおこなわれたそれを、無理やり犯されたのだと騒ぐようなものだ。
気の遠くなるような痛みが、局地的な熱さに変わり、耐えやすくなる。
ひとつ、ふたつ揺さぶりに耐えるごとに、今度は体の奥に疼きの芽を感じる。
痛みは何処へいった。阿含は狼狽した。
みっつ数えるうちに身体はその刺激をはっきりと欲していた
叢の中にあったのは欲していたものだった。
自分が何者なのかなどと考える余地もなく、内臓がただ黙々と与えられた栄養を分解し吸収するように、肉体に与えられた刺激を自動的にむさぼった。
兄の顔を思い出す暇すらなかった。
ただ、一度だけ、赤い欄干の橋をすべるように通り過ぎる影があった。
立ち漕ぎで自転車に乗るそのシルエットは長めのスカートを履いていて、衿元はぱたぱたとなびいて見えた。
それが自分と同じ中学の女子生徒の制服だと気付いた。
その時だけは、肝が冷汗をかくように強張った。
対岸の学習塾からの帰りなのかもしれない。その事実もまた阿含を動揺させた。
しかし夢中になった獣どもはそんな阿含の変化には「幸い」気付きもせず、休むことなく阿含の上でうごめいていた。
兄と机を並べているかもしれないその人影に露見する可能性に畏れ戦くその間も、阿含の身体は容赦なく揺すぶられ続けた。
凍りつくような内側と、焦げ付きそうな外側との温度差に、気が遠くなった。
幸い橋を渡った自転車はこちら側へ来ることはなかったが、曲がる瞬間にかけたらしいブレーキのキィという高い音を聴いた時、阿含は限界に達した。
翌日の雨の校庭に兄の姿はなかった。
ただ桜が雨に打たれつづけるだけの無人の泥地だ。
室内授業へ変更にでもなったのか、または最初から体育館での授業だったのかもしれない。
体育だからといって必ずグラウンドにいるとは限らないのだ。
たとえ正確な時間割が頭に入っていようと、登校拒否児の阿含にはわかるはずもなかった。
フェンス沿いにぐるりと回れば、ボールをつく音くらいは聞こえるかもしれないが阿含はそれをせず、学校から遠ざかった。
もし、何かの間違いでこの借り物の傘とナイロンパーカが兄の目に映るようなことがあったら。そう思ったのだ。
「何これ」
菜箸の手を止めて振り返った母親の顔には、なんとも言えないバツの悪そうな表情が浮かんだ。
「雲水が?」
俺は何でもないことのような素振りで薄いパンフレットを手に取った。
母親は観念したかのようにガスの火を止めた。
「ええ…行きたいって言うのよ。神奈川の学校よ、それ。
遠いでしょう。全寮制だからってあの子言うんだけど」
早口で一気にそういうと困惑気味に俺の手にあるパンフレットを見た。
表紙には真正面から撮った大きな門が映っており、その古い木材でできた四角いフレームの奥には小さく寺の本堂のようなものが、まるで待ち構えているように建っている。
観光案内にしては筆文字の印象がいかめしすぎるようだし、もし寺に修行僧を募集するパンフレットという物が存在するとすればこんな感じのデザインになるのではなないか。
少なくともそれは一般的な入学案内のそれとはかけ離れていたし、学校名も聞いたことのないものだった。
雲水がどのような過程を経てこの異様な、それも県外の学校へたどり着いたのか、俺にはまったく見当がつかなかった。
雲水とはここしばらくまともに話す事などなかったのだから、推し量るには情報不足すぎた。
「神奈川なら叔父さんも居るから良いだろう、
なんてお父さんは言うんだけど…ねえ、阿含」
「で、雲水は?」
母親の言わんとすることを敏感に察知して、俺は話柄を変えた。
わざとらしく家を見回す振りをして、如何にも用があって兄を探しているような顔をする。
「塾よ」
「塾?日曜なのに?」
雲水は週2日塾へ通っているが、それは水曜の夜と土曜の午後のはずだった。
「増やしたのよ。どうしてもその学校に行きたいからって。
ねえそれよりも阿含あなた、3日も4日も平気で帰らないで、
何処に行ってるの?誰かの家にご厄介になってるなら…」
あの夜の対岸の光を思い出す。
あの夜以降、俺は雲水と顔をあわせることを避けるようになっていた。
用があればできるだけ雲水のいない時間を見計らって帰ったし、帰らない日も続いた。
自然、制服を着る必要もなくなった。
ただ学校にだけは行っていた。学校へ行くといっても相変わらず外側から眺めるだけなのだが。
フェンスの向こう側にいる雲水には何ら変わりはなかった。
夏が近づくにつれて強くなる日差しに、少し肌が焼けたような気がするくらいで、劇的に背が伸びただとか、表情が大人びただとかそういった変化はまったく感じられなかった。
しかし現に。
見知らぬ高校の入学案内を見る。
あのフェンスの向こう側にいる変わらぬ兄とは裏腹に、ここにある雲水の痕跡が俺の中でうまく噛み合わなくなっている。
俺がだらだらと他人のベッドで起き、煙草を咥えて途方もない時間を潰す手立てに思いをめぐらせている間にも、雲水の時間は流れている。
俺が見えていないからといって一時停止しているわけじゃない事くらいは解ってはいるが、いや、解っていないのだろう。
だからこうして今うろたえているのだ。
俺は、俺の知らないところで、俺のいない雲水の時間が流れているということを、俺は甘く見すぎていたのだ。
いよいよ夏が近づいて、雲水は週3日の授業のほかにも塾にある自習室とやらに籠もるようになった。
雲水の受けようとしているあの奇妙な高校は、全国でもレベルの高い男子校で、何だかというスポーツでも有名な学校らしい。
校風は寺のような校舎の印象そのものに厳しいことで有名で、受かれば親としてはなかなか鼻の高い学校であるらしかった。
当初、あの頭の固い親父が県外の学校への進学をあっさり許した事を意外に思ったが、どうやらそういう事らしい。
母親によれば親父は現在、金銭面を含めて全面的に雲水に協力体勢をとっているとのことだ。
俺は父親と雲水のいる夜を避けて、平日の昼間に帰っては着替えを済ませたり腹ごなしをするようになっていた。
母親に、父親には内緒で鍵を持たされていたので、母親がパートに出ている時間にでも自由に帰ることができた。
その日は土曜で、学校は休みだが雲水は午後から塾の授業があり、母親は夕方まで帰らないので、仮眠を取るつもりで家へ向かっていた。
家は住宅街といえば聞こえはいいが、要は田んぼや畑の敷地から少し離れたところに住居が固まって建っている。
その中のそのひとつだ。住居郡はゆるやかなカーブを描いて坂を上る道路沿いに建っている。
その坂の交通量はとても少ないが、所々見晴らしが悪く、もともと交通量が少ないがために、無防備に坂を下ってきた自転車と、ぶつかりそうになる事がある。
その自転車も坂の勾配にまかせて下ってきたらしく、カーブを曲がった瞬間にでくわした俺の姿に驚いてブレーキをかけた。
その音が。
キィ、というやけに高い音だ。
その音には何か引っかかるものがあった。
大げさな急ブレーキの音に反して、俺と自転車の距離はそこまで近くなかった。
カーブはゆるやかで俺自身は自転車の姿をミラーで確認していたのだから、相手は人を轢きそうになって驚いたというよりも、人が居たこと自体に驚いたという感じだった。
ひとけはないものと油断して鼻歌でも歌っていたのだろうか。
道路に下ろした足をペダルに戻すと、自転車は再発進して俺の横を通りすぎざま、ぺこりと会釈をした。
俺は、振り返った。
自転車の主は俺と同じような年頃の女だった。
姿かたちがそうだと言うだけでなく、自転車の前かごには雲水が持っているものと同じ、学習塾のロゴマークのついたバッグが入っていたのだ。
デニムのスカートに羽織った半袖のシャツのすそがはためいている。
自転車を立って漕ぐその後姿がなぜか、どうしても、無関係だとは思えなかった。
変だ。
あの会釈をした時の妙な雰囲気。
それにあの女があれほど驚いたのは「思わぬ所に人がいたから」ではなく「思わぬ人間と出くわしたから」ではなかったか。
何故か、確信があった。
心臓が嫌な音をたてて速まりだした。
家は、すぐそこだ。
阿含がそこに立っていた。
弟の姿ををこうして向き合ったかたちで見るのは久しぶりだった。
髪がすこし伸びたくらいであまり変化は見られないが、そこに立つ弟の風景は切って貼りつけたように違和感があった。
「久しぶり」
思わぬ帰宅に驚いて、反射的に出た言葉は間の抜けた挨拶だった。
阿含は答えなかった。阿含は開け放たれた部屋の入り口に立って、見開いたその目で部屋の中をぐるぐると見回していた。
俺の挨拶は届いておらず、俺の姿は見えていないようだった。
俺はそんな弟の顔を窺がいながら、洋服箪笥の引き出しをそっと押し戻した。
「何か用か?」
そう言うと、阿含は表情の消えた顔をこちらへ向けてしばらくこちらの方角を網膜にうつしていたが、やがてああ、と言った。
次にいくらかはっきりとした口調で「ああ、そうだな」と言った。
久しぶり、に対する答えなのだろうか。
続けて今度は思い出したような声でそうだ、言うと
「学校決めたらしいじゃん」
と言った。
顔にはうっすらとぎこちない笑顔のようなものが浮かんでいた。
確かに俺は夏休みを射程にいれてやっと、進学先を決めた。
俺の脳裏には一瞬のうちに、決定までのプロセスや、決め手や、それにまつわるエピソードや、偶然見たクリスマスボウルのワンシーンなんかが、時系列を無視して一挙に頭に浮かぶ。
そしてそれらを目の前にいる弟とまったく共有していないことに不安と焦りを感じた。
いや、不安ではない、これは罪悪感だ。
俺たちは生まれてからずっと同じタイミングで、進学や行事などの岐路を悉く共にしてきた。
俺や阿含が望んだわけではなかったが、同じ家庭に籍をおき、同じ年に生まれれば自然とそうなるのだ。
けれども俺たちの通っている中学に高校は付属していなかった。
進学先は自分の希望や学力と相談して兄は兄、弟は弟で決めるしかない。
どんな弟がいるか知らないが、君の受験に弟はいっさい関係ないのだと、天才を知らない塾の講師は言った。
高校受験の前では兄弟の優劣はまったく影響しない。
邪魔にもならなければ、助けにもならない。
家に帰りもしない弟の進路を気にして何になる。
それでも決定には罪悪感をともなった。
学校を選んだ理由は、単純に自分の成績が上がった事も影響しているし、全寮制に入ってただ家を出たかっただけかもしれない、偶然目にした昨年の映像が俺をあの高校に結びつけたことも確かだ。
どれひとつ欠けても正確ではないし、どれひとつ理解してもらえる気がしなかった。
今どれだけ言葉を選んで伝えたとしても、無駄だ。
そうとしか思えなかった。
きっとそれは、俺にもっと大きな罪悪があるからだ。
結局俺はまあな、と簡単に答えるだけで沈黙した。
阿含は一歩、二歩、と慎重に部屋に入って来て、再び部屋を見回した。
あきらかに普段の素振りではなかった。
探している。
阿含は「証拠」を探しているのではないか。
それとも俺の中の罪悪感がそう見せているのか。
俺も弟の挙動に便乗して、目線だけで部屋の中を点検する。
机の上、床の上、ベッドの上。
幸い問題はなにもなく、机の上などは塾のテキストや筆記具がバッグに入れっぱなしになっている分、いつもよりも片付いているくらいだった。
ベッドが寝乱れているのはいつもの事だし、床に忘れ物が落ちているわけではない。
しかし阿含はその眼差しを今度は俺に向けた。
先ほど開けかけていた洋服箪笥をちらりと見る。じっと見る。
そのまま、箪笥に目を貼り付けたまま、阿含は言った。
「さっきすれ違ったぜ」
すぐそこで、と窓の方を顎でしゃくって補足した。
俺は、答えようがなかった。
タイミング的にきっとそれは真実だろうし、誰と、となどと聞かなくてもわかる。
惚けてみせるほど必死にはなれない。
なかば自棄気味な心持で沈黙した。
「できたんだろ、女」
女、と言う前に阿含はベッドに視線をやり、言い終ると同時にそこに腰を降ろした。
そして手を伸ばすとおもむろに枕を裏返した。
さっきまで呆然と突っ立っていた人間とは思えないそのひとつなぎの動作に俺が何かできるはずもなかった。
枕の裏からひらりと切り裂かれた正方形が舞った。
確信犯的な行動であるように見えたが、瞬間、阿含は凍りついた。
みるみる頬は白く、目には酷く傷ついたような色が浮かんだ。
言葉に詰まったにしては長すぎる沈黙を、俺はどうすることもできずただ眺めていた。
「マジかよ」
動揺を吹き飛ばすかのように、阿含は声を出して笑った。
いや、無理をして笑ってみせたのだ。
そしてその空袋を手に取ると、目の前まで持ち上げて眺めた。
「おベンキョーとか言ってコレだもんな」
そう言って裏返しメーカーと商品名を読み上げる。
その視線をひょいと俺に移して言った。
「何これ、オマエが買ってきたの?どんなツラで?
ちょっとやってみてよ」
口早にそう言った弟の目は赤く充血していた。
自分で自分の早口にまくし立てられたのか、言葉に詰まった俺を見る目に苛立ちが浮かぶ。
しかしあくまで悪ふざけを装った口調で「早く」と言った。
「あのな、」
たったそれだけ言いかけただけで、阿含は耳を塞ぎたくなるような大声で「マジで」と言った。
しかし阿含はまるで事前に答えを知らされていたかのように、状況を正しく理解していたようだった。
「マジで!?あの女が用意したわけ?すっげぇー。サカってんなあ」
くっく、と肩を揺らして笑った。
「スッゲーじゃんマジで…」
すぅ、と顔からお飾りの笑みが消えていく。
一瞬の無を経てうっすらと現れたのはやはり笑みだった。
違いは唇は笑みを模して非対称に歪んでいるのにたいして、目だけがやけに静かに澄んでいることだ。
いつの間にか、俺は手首を掴まれていた。
気付けばもの凄い力で握られているのに、掴まれた自分の手首を目にしてもなお、体温が近すぎて見失いそうだった。
「ぶっ殺す」
耳元で脅迫するようなその声を聞いた瞬間に、視界が大きくぶれ、身体には衝撃があり、揺れが止まるとそこには見慣れた天井があった。
殺す、と言われた割に自分が引き倒されたのはベッドの上だった。
しかし次の瞬間には容赦ない体重のかけ方で、阿含が腹に跨った。
跨る動作と同時に阿含は俺の前開きのシャツの合わせ目に両手をかけると、その10本の指が皮膚を突き破って内臓まで達し、そのまま左右に腹を引き裂いた。
声が、出なかった。
声は出なかったが意識が遠のく気配はなく、引き裂かれたのは衣服だけだと悟った。
腹の上には内臓でも血液でもなく、白いボタンがぱらぱらと散っている。
俺は即座に手のひらで弟の顔面をつかむように押しのけ、腹とふくらはぎに力をこめて腰を上げ、腹に乗った獣を振り落とそうとした。
しかし顔を押さえつける俺の手の向こうで、阿含は笑った。
指の隙間からのぞく目は嬉々として見える。
「ハハッ、弱えー」
顔面を鷲づかみにしている俺の手首を、右手でそっと握ると同時に俺の後頭部はスプリングが軋むほどに深くベッドに押し付けられた。
「弱えぇよ、バカ」
鏡のように同じ動作をしても、威力が違うのだ。顔を覆う手のひらが、口と鼻を圧迫して息ができない。
俺は阿含がそうしたように、自分と同じ体格の弟をベッドの上から突き飛ばすことなどできないのだ。
ある時は読んでいたかのように軽くかわし、ある時はその圧倒的な腕力で悠然と俺を押さえこんだ。
その歴然の差を、一瞬で突き飛ばされた時よりもずっと強く、重く、俺は思い知った。
揉み合って骨や壁に身体をぶつけて痛め、体力消耗しているのは自分だけのように思えた。
俺の膝を両脇に抱えるようにして、阿含はベッドから降りると床に両膝を突いた。
引きずり下ろされるかに思えたその動きはそこでひたと止まり、俺はシャツの引っかかった上半身を起こした。そしてはっとした。
「おい、やめろ」
「うるせえ!黙ってろ!!」
俺が瞬時に掴もうとした金髪を振り払うように、弟は唾を飛ばしてそう吼えると、俺を見上げるように睨みつけた。
しかし俺は黙っていられるような格好ではなかったのだ。
身に着けていたハーフパンツは下着ごと腰の下まで下げられている。
弟の髪の金の向こうには自身の黒がみえている。もう一度口を開きかけて、阿含の変化に気付いた。
見上げる顔が泣きだしそうだ。
いや、それは見間違いか。
鼻息は荒く、牙を剥いて噛み付かんばかりの凶暴な顔だ。
しかしそれでも何故か俺には弟が不安と戦っているように見えたのだ。
「だまってろ」
阿含は目を逸らし、今度は静かな口調でそう言った。
俺は、黙ってしまった。
半信半疑の目で、阿含の指が自分の性器に触れるのをただ見ていた。
弟は跪き、震える舌を出して、根元から先へゆっくりと舐め上げた。
体がふわふわとして、目線が頭から15センチばかり上がったように思え、現実感がなかった。現実感がないのに、これが阿含なのだというその生々しい現実は強烈で、睫を伏せて跪くその姿には場違いに体が熱くなった。
最初、弟のその戸惑いが舌の震えとこわばった頬に感じ取れたが、やがて阿含は我をそして俺さえも忘れたように口を遣った。
頬は紅く染まり、額にうっすらと汗をかいて、時折漏れる音にも無頓着になった。
俺は急に感じた限界を、揺れる金髪を掴んで押しとどめた。
様子を窺がうように弟が見上げる。
薄くひらいた口と、水を張った赤っぽい目は、弟がはじめて熱を出した夜を思い出させた。
乱暴で憎まれ口の多い弟が、初めて思うように動かなくなった自分の身体に絶望し、途方にくれたあの顔だ。
俺の中にふつ、と凶悪な気分が湧き上がった。
「阿含、手を突いて後ろを向け」
金属の輪がふたつ付いているのだ。
阿含はあちこちにダメージのある大き目のデニムを、G.Iベルトで履いていた。
そのベルトには穴はなく、厚い布製のベルトはふたつの金属の輪っかでサイズを調整する。
それのふたつの輪が、阿含の腿あたりでぶつかり合って鳴るのだ。
ちゃり、ちゃりという金属音とベッドの軋みはほぼ同時に鳴り続け、時折、くぐもった呻きが混じる。
阿含は悦んでいるように見えた。
シーツを握り締め、声を必死に押し殺すその姿はひとりでは抱えきれないほどの快楽に必死に耐えているように見えた。
試しに、これは苦痛に耐えている姿なのだと思って見ていても、呼吸のために最低限漏れる息は甘すぎ、真っ赤に染まった耳と、汗でTシャツの張り付いた背中が健康的すぎた。
それに阿含はすでに一度達していた。
前に手を伸ばして触れてみると、案の定それは再び張り詰めていて、阿含は身体を震わせて呻いた。
ベッドに吸収された声が足元で拡散する。唯一苦しげなのは、自由に声を出せないことくらいだ。
「阿含、声出せ」
阿含は動かなかった。
むしろいっそう声を押し殺したようで、金属のぶつかる音とスプリングの軋む音だけが大きく響いて聞こえた。
「阿含、顔あげろ」
手を伸ばせば髪に届く、腕に届く。
この体制からならばいくら阿含とはいえ、無理やりに顔を上げさせることは可能かもしれない。
けれども俺は絶対にしない。
俺はこの強い、誰よりも強い弟に、言い訳を与えてやるつもりはない。
いいや、もっと低く這い蹲れ。
「阿含」
ほんの少し、強く突く。
金属音とスプリングのリズムが乱れる。
ひ、と泣くような声が漏れ、阿含の頭がほんの少し持ち上がった。
蓋を失った口からはだらしなく声がだだ漏れになり、金属とスプリングに合わせて何度か喘いでみせたが、唇でも噛んだものか再び聞こえなくなった。
少し早めた速度を、元に戻し、元の速さよりも緩慢にする。
ベルトの金属音はメトロノームのように忠実に音の間隔を広げた。
止まるほど長い間隔になった時、阿含が口を開いた。
「ち…っくしょ、わかったよバカ」
「お前また、なんだろう」
「うるっせーよ」
羞恥で赤くなった頭皮が金髪の向こうに透けて見えそうなほど、上ずった声だった。
ことさら喘ぐ場所を強くしてやると、阿含は簡単にだらしなくシーツの上に二度目を放った。
「お前…よくそんな事ができるな」
学習机の上にはテキストや参考書が広げられ、漫画や雑誌の並んでいた本棚に今は辞書や教科書が収まっている。
「必勝」の半紙さえないものの、兄のまわりは受験一色だ。
だからと言って、俺まで同じ事をする必要はない。
「…しょうがねえじゃん」
兄に迷惑がかかるわけではないし、俺が責められる謂れは何もないのだが、雲水はわざとらしく長く息をついて、くるりと椅子を回してしまった。
こちらに背を向けてテキストに視線を落としたまま言った。
「だいたいお前、なんで制服着て今帰ってくるんだ。
学校が終わって何時間たったと思ってる」
まあ、4時間くらい?と惚けると即座に「お前の内申書が見てみたいよ」と嫌味を言った。
憎たらしい背中に目をやると、ベッドの枕元に置かれた入学案内が目に入る。
俺がこんな目に遭うのは全てこれのせいなのだ。
「お前がどうしても行くっつーからだろ、だいたいなんだよコレ」
手に取ってベッドに腰を下ろすとページをめくる、所在地の簡単な地図と一枚の写真が載っている、パンフレットの最後のページだ。
「この地図見る限りすんげー駅から離れてるんですけど。
しかも何?この空撮写真。秘境かよ。世界遺産じゃねーんだよ。
マジで修行でもする気かっつの。ここよか山奥じゃん。
神奈川ぜんっぜん意味ねーよ」
「うるさいぞ、推薦入学のお前と違って俺は今が大事なんだ。
とっとと出てけ」
振り向きもせず、ご丁寧に皮肉まで織り交ぜて一蹴すると、シャープペンを走らせるシャリシャリという音だけが響いた。
嫌ならやめろ、と言われなかっただけまだマシか。
しかし珍獣扱いされながらも通学を再開し、首尾よく推薦入学枠を手に入れて来たというのに面白くない。
机に下がった学習塾のかばんには学業成就の白いお守りがついていた。
いつ行ったものか、県内の神社のものだ。
「なあ、お前らまだ付き合ってんの?」
返事はなかった。返事がないので、部屋を出て行くのはやめた。
ベッドにそのまま横になって、パンフレットをぱらぱらとめくる。
「むこういったら超遠距離じゃん」
ここと神奈川では「超」がつくほどの遠距離ではないかもしれないが、なまじ近いだけに新幹線だとか飛行機ではなく、電車での移動しかない。
下手をすれば北海道や沖縄へ行くのと変わらない時間がかかるのである。
「やめれば」
どうせ無視され続けるものと思っていたが、ほんの少し間をおいて返事が返ってきた。
「お前こそ」
しかしこちらを向いた様子はない。
「どうせ今まで一緒だったんだろう。あの北高の生徒と」
ぱらり、テキストをめくる音がする。
「お前が学校へ出るようになったから、放課後に会ってるんだろうが、
こんな時間に補導でもされればさすがに内申に響くぞ」
階下でぱたぱたと小走りな音が聞こえる。
阿含ー、お風呂入っちゃいなさーい。
母親はしばらく階段の下で俺の返事を待っていたようだが、やがてあきらめたらしく遠ざかる足音が聞こえた。
計算式でも書いていたものか、絶え間なく続いていたシャープペンの音が止まった。
ギィと椅子が軋んだ。
「お前まさか、俺が気付いていないと思ってたのか?」
end.