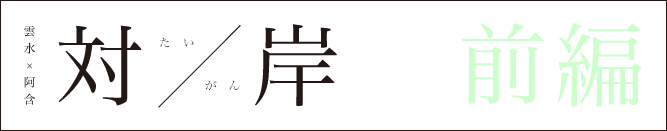もっとよく見ようと、一瞬の表情をより鮮明にとらえようと、目を凝らし瞬きも忘れ、切実に凝視する。
うしろから肩を叩かれ、雲水は振り返る。
すこし耳を寄せろと手振りされると、素直に従った。何を吹き込まれたものか、そうすることがこの世のならいであるように、雲水はすこしだけ、肩を揺らした。
きっと、笑ったのだろう。
そのあいだに彼の属する列が進み、雲水もまた促されて一歩進んだ。
列のなかの兄は、見つめる俺の存在に気付いていない。
彼の目に映るのはあくまでハンドボール投げや、走り幅跳びといった記録更新にはげむクラスメイトと、うすぼけた葉桜の校庭である。
サボリ魔の弟が学校の敷地外から自分を見つめているかもしれない、などと思い、校庭を見回す…という事はまず一切ありえない。
だからこそ、俺はその横顔を安心して見ていられた。
俺は兄の姿を見ているが、兄が俺を見ることはない。
それこそが俺の葛藤であり、安息だった。おまえに夢中になっている俺を、おまえは知らない。
ここははるか対岸なのだから。
「オマエは3年、何組?」
声に振り返ると、すでにその箱は弧を描いていた。
俺はあせった振りをして、フェンスからすばやく手を離し、それを受け止めた。
事実、俺は焦っていた。
もちろん、投げられた煙草の箱を取り損なうからではない。
柵のむこうに不意に見つけた兄の姿を追うのに夢中になりすぎて、油断した。帰ってくるとわかっていたはずの人間を失念していた。
俺はしがみついていた金網にまるで手のひらを返すように、わざとらしく背中を向け、それに寄りかかった。
老朽化したフェンスは頼りなく、予想よりも大げさにたわんだので、俺は危うくバランスを崩しそうになった。
その無様さはまるで、小便のあとに後ろ足で砂をひっかける犬に似ている。
おかしな話だ。犬はなにも、羞恥の為に小便のしるしを隠蔽しているわけではない。
サボリ魔の不良中学生が、クラス替えしたばかりのの初々しい同級生をうらめしげに眺めていたって、誰も気にしやしないというのに。
金網にかじりついて校庭を眺めていたからって、心の奥底までもがにじみ出すわけではない。
しかし、一度はね上がった心臓が落ち着きを取り戻すまでにはすこしの時間が必要だった。
俺はわざとらしく煙草の箱にまとわりつく薄いビニールをばりばりと音をたてて剥ぎ、急いたふうを装って黒い学ランのポケットをさぐった。
「進級はしたんだろ?一応」
煙草を投げてよこした男は俺の黙殺など気にもかけず、煙といっしょくたにそう吐くと、自分のグレーのジャケットから、安っぽいピンク色のライターを取り出りだし、親切にも投げてよこした。
受け取って火をつけ、すぐに投げ返す。
いやあ驚いた、ここはまるでミネラルウォーターのCMの世界だなあ。
それは昨年結婚して家を出た、姉貴の男が言った台詞だ。
東北地方に分類されるのをギリギリ免れたこの土地の豊富な自然。
その濃い緑に洗われ続けて汚染される暇もない澄んだ空気に、副流煙をまぜこむ事でいくらか気が晴れた。
俺はこの春から、登校拒否をしている。
これまでの出席率もとても良いとは言えなかったが、三年になったこの春からは「学校へ行く」という選択肢を完全に断った。
家を出る口実として学ランを着ているだけで、このフェンスの向こう側へは一歩も足を踏み入れていないし、踏み入れる意思もない。
登校を避けているというよりは、意識的にこちら側に身を置いている、と言った方が真実により近い。
この柵のむこう側には雲水がいる。
「阿含、来年ウチの高校来いよ」
胸にエンブレムの入った、グレーのジャケットが言った。
それはここのすぐ側の公立高校のもので、そのジャケットを身につけたこの男は、その高校の生徒ということになる。
「ハッ、わざわざバカ高受けるほどヒマじゃねーよ」
俺は今日初めてこの男にまともな返事をした。
さめた面をつくっても、むきになっているのが見え見えで我ながらうんざりしたが、幸い男は言葉の方に食いついた。
「じゃあどこ受けんだよ、第一?西高?それとも将来は東大でも目指すつもりかよ?」
奴は煙草をはさんだ手をブラブラと振りながら、わざとらしく道化た。
内心舌打つ。
思いのほか痛い所を突かれた俺は、得意の黙殺を決め込んでこの場を切り抜ける覚悟をしたが、突然、男は啓示でも受けたかのように話題を変えた。
「そういやさっき」
話題の変わった事に安堵したが、入れ替わるように現れた男の表情に、嫌な予感がする。
これから変わる表情の変化を見逃さないよう、今の顔をよく見ておこう。男の弛んだ目の色はそう言っていた。
「ずいぶんイッショーケンメー見てたじゃんよ。向こう側」
冷蔵庫に貼られた、三者面談の時間表を見たときから、阿含は嫌な予感がしていたのだ。
おそらく進路についての話し合いがなされるであろう、担任教師と生徒、そして親の三名で行われる面談は、15時30分から兄の雲水、そしてそのすぐ下の16時の欄には阿含の名前が書かれていた。
「まさか双子で同じクラスとはな」
父親のその一言で、その後のシナリオは決まったも同然だった。阿含はまだ食べ始めたばかりの夕食をできるだけ手早く済ませるため咀嚼を早めた。
「こういう時には時間の融通もきくし、私は助かるけど、先生は大変よね」
父親のシナリオ進行にもっともふさわしい台詞を吐くことにかけて、母の右に出るものはいない。おそらく無意識のうちに染み付いているのだろう、この繰り返され続けるたったひとつのパターンが。
酌とともに母から最高のフリを受けた父は、いつものタイミングでいつものように鼻を鳴らす。
まるでお約束の見せ場のようなその表情は堂に入った嫌らしさで、唇は笑みの形をしているにも関わらず非対称に歪み、目は醒めたふうを装いながらも、血の臭いを嗅ぎ付けた鮫のように爛々と輝いている。
嘲笑。
阿含は、父親といえば即座にその顔が思い浮かぶ。
「まさか見間違える、なんて事はないだろう」
父親が大げさにそう言って見やったのは、阿含の目の覚めるような色の髪だ。
この保守的な田舎町で、金髪は未だにひどく目立つ。
都心では単なるファッションとして処理されるだけのつまらない色が、ここでは反抗と退廃の意思表示とみなされる。
もちろん、15歳の阿含は決して素直で従順な中学生とはいえないし、むしろレッテル通りの反抗的で退廃的な少年である。阿含もそれについて異論はない。
「お前たち、進路は決まってるのか」
中学三年の三者面談をひかえて、当然の流れともえいる父親の言葉に、阿含の味覚がほぼ完全に遮断された。
噛む米の味はなくなり、あたたかな飯は途端、口の中に無理矢理つめこまれた得体の知れない糊状の何かに変容した。
異物を口に含んだ阿含の喉は、それを拒むかのようにぐっと狭まり、たった一口を飲み込むことさえ難しいほどだった。
それはほんの数秒前まで、空腹の少年の腹を満たすはずの母親の料理だったというのに。
しかし、父は続ける。
「雲水、おまえ行きたい高校あるのか」
「…まだ考えてない」
今、これ以上なにかを口に入れる気にはとてもなれない。
阿含は口の中に残っている異物は、実は食物なのだと言い聞かせ、健気にもどうにか飲み込んだ。
そして心の片隅で、強烈に祈った。
どうか「この次」が来ませんように。
しかし例外はあり得ない。「この次」は必ず来る。頭のどこかでは、津波に怯えながら眠るようなあきらめがあった。
「早く取りかからないと、入りたくても入れなくなるぞ。
自分が阿含と同じだと思っていたら大間違いだからな」
背中や胸に一気に汗が吹き出す、かといえば頭が冷たくなるような、気が遠のくようなめまいが阿含を襲った。
かろうじて箸を置こうとする、手が震えている。
隣に座る兄の手元も、固まるように停止していた。その横顔を、阿含は盗み見る。
坊主頭の眉は険しいが、目は不安げにせわしなく揺れている。口は耐えるように固く結ばれ、頬の筋肉ははりつめていた。
慣れない。
こんな事は何度でもあった。
しかし、けっして慣れる事ができない。立つ位置はまるで逆だというのに、阿含は雲水と同じように、いや、雲水本人以上に萎縮し、どうしようもなく逃げ出したかった。
しかし幕はまた降りてはくれないようだ。
「だいたい塾にまで行っていてどうして…」
父親の言葉にじっと耐えるようにうつむいた雲水と、ふいに、何かの偶然のように目が合った。
瞬間、安全装置がはずれたように、阿含は拳を振り下ろしていた。
今日の食卓には、各自に牡蠣とエビのフライが2つずつ、キャベツと一緒に白い平皿にもりつけられていた。
その皿のちょうど9時の位置を、阿含の左の拳がかすめた。
かたく握った15歳のこぶしが合板のテーブルを打ち付けるのと同時に、メインの皿が跳ね上がった。
皿は悪夢のような速さで半回転すると、うつ伏せに着地した。
割れた食器は一枚もなかったが、瀬戸物や汁物でひしめくテーブルで翻ったセラミックの皿は、禍々しくキャベツをばら撒き、凶暴な音を立て、ほんの一瞬であたたかい夕食を生ゴミに変えた。
一家そろっての夕食の時間という日常を破壊した阿含は、何も考えられない頭のまま、誰の顔も見ることなく逃げるように椅子を引き、二階の自室へ引き上げた。
しかしドアを、自室のドアを閉めようとした瞬間、追ってきた足音が阿含に追いついた。
「なんだよ」
うんざりだという声を出しておきながら、ドアノブを離してしまうのだから情けない。
追って来てくれるのを期待していた自分の心が透けて見え、またも阿含は自己嫌悪した。
兄は、唐突に言った。
「学校こいよ」
その言葉を聞いてうろたえた阿含が反射的にとった行動は、父親と同じあのしぐさだった。
小馬鹿にしたような冷笑。しかし、目は逸らしたままだった。
「意味わかんねえ。同じクラスだぜ?"俺"と同じクラスなんだぜ。
その意味、わかってんのかよ」
顎を上げて、酷薄に口の端を吊り上げてみせる。
こうすれば、余裕綽々、高慢に見える、そう見えれば相手が萎縮する、言う事を聞く。
遺伝のせいにする気はないが、いつだって後悔するのはやった後だ。
阿含はできるだけ早く、その表情を引っ込めることのできるタイミングを探した。
しかし、それにしても。学校は一体どういうつもりで自分達のような兄弟を同じクラスにしたのか?
この春発表されたクラス割りに、誰よりも動揺したのは阿含だった。
俺と雲水を同じクラスに、同じ柵に入れる。
ぞっとした。
決して仲の悪い家族ではないのだ。それでも、こうなる。
それが他人の中で、狭い狭い金魚鉢のなかでどうなるのか、阿含は想像することすらも拒絶した。
しかし、兄は言うのだ。学校へ来い、と。
「知っているくせに、はぐらかすな」
「なにを」
雲水の視線はおそろしいくらい真っすぐで、我ながら子供じみていると思いながらも、阿含は視線をはずしたままそう言うのが精一杯だった。
雲水がため息をつく。こっちを向けと肩口を突くように押される。外した視線を守る為には、より首を曲げなければならない。
雲水はすぐに視線の先など諦めたというように手を伸ばし、阿含の髪にふれた。
色素を限界まで抜いた、油気のなく頼りない髪に指を通す。何も言わない。
指は阿含の髪を櫛のように梳き、そのまま頬をなでて、耳と顎をつなぐ線を辿った。
酷くやわらかい触れ方が、知っているくせに、と阿含を責めていた。
阿含が息苦しいほどそう感じるのは、雲水の自分への気持ちを知っていたからかもしれない。どろりと重たく、火照りの蓄積した兄の自分への執着。
目は未だ逸らしたままなのに、いつのまにか唇は触れ合っていた。
表皮が触れ合っただけなのに、阿含の眉は切実に歪んだ。
春が来れば冬の眠りから覚めざるを得ない虫のように、阿含はもはや能動的にならざるを得なかった。
押し当てられた唇にみずから舌を押し込み、兄のそれに絡める。
それは阿含の意思とは、まだ眠っていたい気持ちとはまるで無関係に、動いてしまうものだった。 そして雲水も当然のように受け止める。
どれだけ目を逸らし続けても、どれだけ言葉で距離をおいてもしても、さらけださざるを得なくなる。そういう力が雲水の体温にはあった。
雲水は弟の顎を割れるほど強く引き寄せ、阿含は兄の項を爪が食い込むほどに強く掴んだ。その姿は二匹の生き物に似ていて、気難しい思春期の少年には似ていなかった。
漏れる息がどちらのものか、もはや本人達にも区別がつかない。
雲水はあいた手で阿含の脇腹のシャツを掴むと、もどかしげに引き上げた。途端、阿含の身体がびくり、と揺れる。
何か言おうとして、阿含は声を出しかけたが、雲水がそれをすぐに舌で絡め、阻止した。
無理矢理という程ではないにしろ、強引に引き上げられた阿含のシャツから、ぶち、と糸のちぎれる悲鳴がきこえた。
ボタンを留めていた糸がたまたま朽ちかけていたに違いないが、阿含にはその音が巨大に響いて聞こえた。
舌のこわばる阿含と対照的に、雲水はその音を聞いたからにはもう後戻りはできないとばかりに手のひらをを弟のシャツの中に滑り込ませた。
肌は常にシャツという繊維に触れている。
街を歩けば人に触れることもある。
ケンカになれば力のかぎり掴まれる事もある。
しかし、日常のどの瞬間にも、ここまで皮膚感覚が研ぎすまされる事はない。それが兄の、雲水の手のひらなのだと理解した瞬間、何兆という細胞のひとつひとつが、意思を持った生き物として一斉に目覚めた。
その指先に辿られた細胞は狂喜して、燃えあがったように熱を発した。
「っ…」
舌からではない、身体の底からの声。出したというよりは鳴った、に近い。
恥じればいいのか、それとも二度と出ないよう注意すればいいのか、選ぶ余裕はない。
阿含はただ暴走する皮膚の感覚になかば怯え、しかしその何倍も興奮した。
兄の手のひらが自分の身体の上を思うように滑らないのは、雲水の汗か自分の汗か。
「阿含」
かろうじて唇がれるくらいの位置で自分を呼ぶ兄の声が、まだ半分蕩けたままで、阿含の腰が重くなる。
「はなれたくない」
このまま頭から喰ってしまいたいとでも言うように、雲水はそう言って阿含の耳に噛みつき、やわらかく複雑な形を確かめるように濡れた舌を這わせた。
言葉と刺激で、阿含の身体は生理的に震え、肌はくるったように泡立った。
阿含は自分が兄と、兄によってもたらされる快楽の奴隷であることを知っていた。自分を欲しているその腰を強く押しつけられ、阿含の膝は頼りなく笑った。
「おまえは違うのか?」
焦れたように問う兄の言葉が、瞬時には理解できないほど、阿含は芯から痺れきっており、ほんの小さく促されただけで自分のベッドに腰を下ろしてしまった。
ひとり用の、よくあるパイプベッドだ。
その安手のベッドが、2人分の体重で軋んだ音を聞いた途端、逆上せた阿含の頭からどっと血が引いた。
自分が天井を見ていることに動転する。
濃いもやのたちこめていた意識が、一瞬にして鮮明になった。
阿含は戦慄した。
深い谷にかかった、長い長い吊り橋の真ん中で、悪い想像をした時のような逃げ場のない恐怖だった。
ちっぽけなベッドに押し込められているのはまぎれもなく自分だった。
上に乗っているのが誰であるかなど問題ではない。ましてや、そこに好きだの嫌いだのという感情が入り込む余地などない。
オスである自分の肉体が組み敷かれている。
ほんの数秒まえまで狂喜していた肉体が一転、そのおそろしさに震え上がった。
自分が女にされる事がおそろしいのではないし、実感もない。しかし「向こうが男」なのは確かである。
それは自分の存在を曖昧にする。
兄を好ましいと思う気持ちや、好きなようにさせてやりたいなどという感情は、所詮水面に浮かんでいるだけで、地底からゆさぶられるような生理的な拒絶に、阿含はもろくも打ち負けた。
熱烈に欲されているという恍惚が、性急に自分を求める兄の荒っぽいしぐさが、そっくりそのまま怒濤のように押寄せる。
気付けば、兄はベッドの下に転がっていた。
女ならよかった。
女は自分と同じ体格の人間を、こんなにも簡単にベッドから突き落とすことなどできない。
そんな思いが頭をかすめたが、それはすぐに消え去り、阿含は零コンマを争うように飛び起きた。
開ききった瞳孔でベッドから突き落とされた兄の姿を確認する。強く身体を打ったようだったが、何も聞こえなかった。心臓の音が大きすぎるのだ。
自分もベッドから飛び降りたが、足裏に感覚はなかった。
「阿含!」
出口へ向おうとする背中に浴びせられた声に、阿含は槌で打たれた銅鑼のように震え上がった。
振り返ることはできなかった。いとしい兄の顔を直視することが出来るはずがなかった。
今さらいとしいと思うことは許されなかった。
何度目だ。
こうして逃げ出すのは今日で何度目だ。
掻きむしりたくなるような衝動を抑え、阿含は、少なくとも阿含の肉体は、なによりもこの場から兄のまえから逃走したがっていた。
一瞬、動かない右腕になにが起きたのか理解できなかった。
雲水が掴んでいた。
雲水はまだ中腰のような状態だったが、追い縋るように阿含の右手首を掴んでいた。そう気付くまでずいぶん長い時間がかかった。
たいして鍛えてもいない筋肉が、一気に膨張し、力が湧くのがわかる。
そこに嫌悪のような苛つきがあったことを、阿含は悲しく思った。
しかしもっと悲しいのは、自分があまりにも軽々と兄を振り払えることだった。この世に自分が拒否することのできないものなど無いのではないだろうか。
阿含の右腕に縋った雲水の左腕は、おおきく弧を描くようになぎ払われ、雲水は再び阿含に突き放された。
背後にあった学習机に後頭部を打ち、小さく呻いた雲水の声が、今度は阿含にもはっきりと聞こえた。
胸が痛んだ。
痛んだからこそ、阿含はそのまま部屋を出て、転げるように階段を降りた。
ほどいたままの靴紐を結びもせずにつま先をひっかけ、もどかしくチェーンロックを外し、生温い春の外気を吸い込んだ瞬間、阿含は恋しさで身が千切れそうになった。
灼けるような熱さがこみ上げる。 今すぐ駈け戻りたかった。けれど、できるわけがない。
この気持ちは本物なのに、愛だの恋だのと言えるのは所詮、こうして手の届かない場所まで離れた時だけだ。
お前を目の前にしたら俺は逃げ出してしまう。
自分とお前を天秤にかけて、あっさりと俺は自分かわいさにお前を棄ててしまう。
思いが通じることはないのだという真っ暗な気持ちと同時に阿含は安堵してもいた。こっち側までくれば大丈夫だと、心底ほっとしていた。
どうせ無駄なのだと言い聞かせた。
しかしフラッシュバックのように、最後に見たような気がした兄の顔がちらついた。だからせめて、阿含はできるだけ音を立てないよう玄関のドアを閉めた。
聞こえただろうか。
兄は向こう側で、この音を聞いただろうか。
阿含はしばらくのあいだ茫然と、二階の電気のついていない窓を見上げ、その暗闇に兄の姿を探していた。